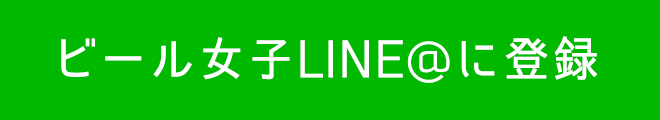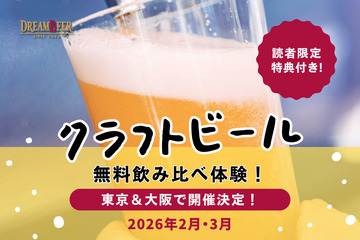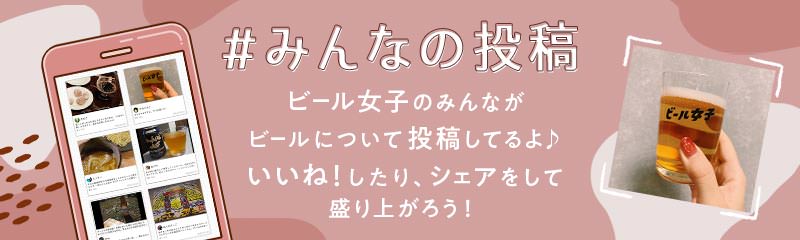sponsored by ISLAND BREWERY

長崎の離島・壱岐島と、そこでビールをつくる「ISLAND BREWERY」の魅力を伝える特別連載『壱岐クラフトビール旅』。
1回目の記事に続き、2回目は、「ISLAND BREWERY」の代表でありブルワーである原田知征さんにインタビューを敢行しました!
「壱岐クラフトビール旅」特集ページ
壱岐の島で誕生したクラフトビールブランド「ISLAND BREWERY」。

島の魅力を伝えるビール造りに挑戦し、今や長崎を代表するクラフトビールへと成長を遂げています。
今回、代表の原田さんに、ブルワリー立ち上げの経緯から壱岐島を取り巻く課題、そして未来についてのお話など、たっぷりお話を伺いました。
焼肉屋さん、実家の酒造業からクラフトブルワリーへの転身

―まずは、ビールづくりを始めることになった経緯を教えてください。
原田さん「もともと実家が焼酎や清酒をつくる酒造業を営んでいたので、いずれ継ぐため、東京農業大学に進学し勉強しました。ただ学生時代は焼肉が好きだったので焼肉屋でアルバイトをしていました。ちょうどその頃、焼肉屋が商社に買収されることになり、「大学を卒業したら社員にならないか」と誘われたんです。でも、いつかは島に戻るつもりでしたし、アルバイトのままでも時給が良かったので、一度は断ったんですよ。ただ、「今の手取りと変わらないなら社員になってもいいですよ」と冗談で言ったら、まさかの社長決裁が下りて(笑)、そのまま焼肉屋の社員になりました。
―焼肉屋さんではどのような経験を?
原田さん「焼肉チェーンの店舗管理を任されて、数字の管理や原価率、人件費の計算などを学びました。その経験が、後に実家の酒造を継いだときにすごく役立ちましたね。実家ではどんぶり勘定で価格を決めていたので、僕が学んだ知識を活かして価格設定を見直したりしました。そこで2年ほどの間に東京で3店舗ほど立ち上げて、実家の方に戻りましたね」

―そこから、なぜビールづくりへ?
原田さん「前職の酒造会社はいくつかの会社が協業してできた会社なんですが、共同経営の難しさを痛感したことが大きいですね。要は社長が何人もいるような会社で、意見の食い違いは日常茶飯事でしたし、いろんな意見が飛び交う中でなかなか自由に動けない状況でした。そんななか、会社内の統制をするよりもっと外向きに力を使いたいと思うようになって、独立を決意しました。それに、壱岐にはすでに焼酎蔵が7軒もあったので、あえて違う道を選ぼうと思ったんです」

―さまざまなお酒の中でもなぜビールに?
原田さん「壱岐島は夏にお客さんが多くいらっしゃる島で、ビールがあったらもっといいんじゃないかと思ったこと。また、当時47都道府県で唯一クラフトビール醸造所がなかったのが長崎なので、ビールがあったらおもしろいんじゃないかと。家業が同じ発酵つながりというのもありますが、ビールに焦点をしぼり動き出しました」
―私たちの間でも、「長崎にやっとクラフトビールブルワリーができた!」と話題になっていました。
原田さん「長崎って古くから外国と外交や貿易をして、さまざまな文化が入ってくるのに、意外と保守的なんですよね(笑)」
―そうなんですね…!
原田さん「百貨店で各県の物産を集めたイベントの際、『長崎だけビールがないんですよね』と担当者の方から聞いて、冗談半分で『僕がつくりますんで』って言っていたんです(笑)」

―「魚に合うビール」というコンセプトがとてもユニークで、特徴として焼酎に使われている白麹を使用しているということですが、これもやはり、焼酎を生業にしてきたご実家への想いなどがあるのでしょうか。
原田さん「じつはこれってたまたまなんです」
―え、そうなんですか?
原田さん「長崎県は、とれる魚種は全国1位といわれるほどのお魚県なんです。せっかくさまざまな魚がとれる県に住んでいるし、魚に合うビールっていうのもあまり聞いたことがない、その上で尖ったビールをつくりたいと思って“魚に合うビール”って面白いと思ったんです」

―味わいの方向性はどうやって決めていったんですか?
原田さん「壱岐島にある『みなとやゲストハウス』の魚好きの店主に協力してもらって、魚料理を用意してもらい、僕は日本全国からさまざまなビールを50種取り寄せて、ペアリング会を開催したんです。じつは僕アルコールに弱いので、みんなの意見を聞きながら試していったんです」
―50種類はすごい!
原田さん「そのなかで、忽布古丹醸造さんのビールで、柑橘が香るとてもすっきりとしたビールに出会って、この味わいは魚に合うんじゃないかと思ったんです。同時に、赤ワインのペアリング料理が肉ですよね。逆に白ワインは魚。つまり、白ワインみたいな酸味と、ホップの柑橘が混ざり合ったら、魚に合うおもしろいビールができるんじゃないかと思ったんです。『白ワインの酸味=クエン酸……白麹!!』っていう流れで思いつきました」

―求める味わいが、結果的にご自身のルーツに戻ってきたんですね…!
原田さん「ただ、酸味ってどちらかといえば、酸化という意味でビールにとってはマイナスの要素じゃないですか。だから、思いついたときはまったくどうなるか想像できていなかったし、酸味をビールに出すことがいいことなのかという不安もありました。そんなとき、僕の先生である小林くんに出会ったんです」
原田さん「ビールをつくろうと思いたったとき、最初はアメリカに修行に行って修行をする予定だったんです。ただ、ちょうどコロナ禍とかぶり、渡航制限がかかってアメリカに行くことができなくなって。どうしようかと思いつつ、オープンの日取りなどをある程度決めて、ブルワーになってくれる人の募集をかけたんです。最初は「島好き」「ビールつくりたい人」で募集をかけたらすぐ応募があると思っていたんですが、考えが甘くて、全く応募がなかったんですよね」

―なんと…!
原田さん「いよいよどうしようと思ったとき、北海道のブルワリー・Brasserie Knot(ブラッスリー・ノット)の植竹さんにセミナーでお会いすることがあって。この人だったらお願いしたいと想い声をかけたんですが、ご自身も立ち上げにお忙しい時期で難しいとのことで。だけど、一番弟子の小林くんならいいよと言っていただいて。まだそのときは会ったこともなかったんですが、会ってみたら彼が農大出身の後輩だということがわかったんです」

―同じ農大の先輩と後輩…!
原田さん「でも、ビールづくりにおいては先生なので。3ヶ月という約束で小林くんと一緒にビールづくりをはじめましたが、いろいろあって結果6ヶ月一緒にビールをつくってくれました」

―白麹を使うと言ったとき、小林さんはどんな反応でしたか?
原田さん「やっぱり『酸味が強くならないですか』って言われましたね。それに、ビールをつくる人ってpH(ペーハー/ビールの味と見た目に直接影響する値のため、ブルワーはpHの値を重要視する人が多い)をとっても大切にするんですよね。焼酎をつくっていたときpHはほとんど気にしたことがなかったので、最初は小林くんと考え方が全然違ったんですが、最終的には麹の力も相まって良い化学反応が生まれて、おいしいビールをつくることができました」」
長崎に久しぶりに誕生したクラフトビールが広げる新たな可能性

―具体的にどのような場所で提供されていますか?
原田さん「県内の有名ホテルやクルーズトレインでも採用されています」

―それはすごいですね!
原田さん「魚と合うっていうところに興味をもっていただいたところもあります。あとは、長崎・小浜の伊勢谷旅館さんは真っ先に知っていただいて、生で提供したいとサーバーを置いていただいています。旅館に泊まったお客様で、壱岐島まで足を運んでくださった方もいたりして、それはとても嬉しかったですね。そこから知っていただいて、他のホテルさんも提供していただいていますね」

― 他販売チャネルでいうとどこでしょうか?
原田さん「あとは、オンライン販売もですし、長崎空港の社長さんなんかも気に入ってくれて販売していただいていますね。『日本のなかでおいしくビールが飲める空港にしたいんだ』っておっしゃっていただいて。」
―長崎空港だと、壱岐島に来る時にも使う空港だったりしますよね。
原田さん「そうですね。やはり空港で販売していただいていると、お客さん的にはお土産に持って帰るにはちょうどよいんですよね。ビール的にも冷えた状態で持ち帰れるっていう点もありますしね」
代々受け継がれる、ビールへの想い

―ひとつ気になることがあって。最初にビールをつくるって宣言したとき、家族は反対されなかったんですか?
原田さん「母は賛成だったんですが、父は大反対でした」
―え、そうなんですか…!
原田さん「理由としては、地ビール時代を知っているから、絶対に儲けにならないって思っていたんだと思います。それに、そもそもおいしいビールはつくれないだろうと。地方に出向いたとき、たぶん地ビールなどを飲んだんだろうと思ったんですが、おいしくないっていう印象も強かったんじゃないかと思うんです。だから、外堀を埋めるように『ビールづくりなんかやめさせるように』って言ってまわっていたと聞いています。ただ、僕の意思は固かったんですが、そんななかで親父が亡くなって。こういってはなんですが、まだ生きていたら、今ビールはつくれていないかもしれません」
―ただ、絶対天国からよくやったっておっしゃってくれていると思いますよ…!
原田さん「言ってくれているといいんですけどね(笑)代々という意味で言うと、僕の息子が今度、僕の母校である農大に行くんです」
―ブルワリーを継ぐためですか?
原田さん「だと思うんですけどね。ビールってかっこいいっていうイメージが先行しているのかなと思いますが」
―お父さんの背中を見て…!そして、同じ大学に通われるのも嬉しいですよね。

原田さん「1日12時間働いてやっと利益がトントンになるかならないかの世界だけど、そんなにきついことができるのかとは言っているんですけどね。僕はビールづくりが好きだからできているけれど、好きじゃないとできない仕事だよとも言っていて。そもそも息子に継いでほしいと思って始めたわけでもないし、何か他にしたいことがあればそれをしてもいいと思っています。ただ、ブルワリーを継ぎたいなら、農大ならお酒関係の友達もたくさんできるし、ひとつの選択肢としていいんじゃないという話をしたら、農大に決めていましたね」
―先輩も後輩も、いろんな知識をもった方がいらっしゃいますもんね。
原田さん「何か困りごとがあったとき、人に聞けばどこかに繋いでくれるし、すぐに返ってくる。先輩後輩関係なく、たくさんの人と繋がれるぞと。全然違う話ですが、今度農大出身ブルワーがいるブルワリーを集めた“農大ビールフェス”を農大で開催する予定なんです」
―え!それは楽しそう!!というか、農大出身のブルワーって結構いらっしゃるんですね。
原田さん「結構いますね。イベントの詳細はお楽しみに」
原動力はどこから?

― どこからその原動力は生まれてくるんですか?
原田さん「なんだろう。結局は島が好きだって言うことだと思うんです。正直高校までは、『こんな島は早く出たい』って思ってたんです。遊ぶ物は何もないし、面白くない、都会みたいなキラキラした街並みもない。できるだけ早く島を出て東京に行きたいって思っていました。実際、東京に出てからは、東京での暮らしも楽しかったんです。ただ、マンションに住んでいて隣の人も知らない、どこかにいても誰彼話しかけるわけでもない。なんだかつまんないなって思えてきて」

―確かに、人の接点でいうとぐんとなくなりますよね。
原田さん「あと、僕はイカ刺しが大好きなんですが、東京のスーパーでお刺身を買おうと思ったら、真っ白いイカしかないんです。てっきり湯引きしたイカだと思っていたら『これがイカ刺しですよ』って言われて。壱岐島の透き通ったイカ刺しとはまったく違ったんですよね。あとは、壱岐島の魚がいかにおいしいかをまざまざと感じて、島の外にでて改めて魅力を知りました」
―壱岐島の魚介、本っ当においしいです。
原田さん「それに、壱岐島の人口がどんどん減ってきてしまっている現状を変えたいなって思ったのもあります。あるとき、『なんで島から人が減っていってしまうんだろう』と考えたら、職場がないからだと気づいて。若い子たちが働きたいと思う職場や、そもそも働き口がないんです。酒造や酒屋もそうですが、自営業や家族経営のお店が多いですし、僕の家のように家と店が一体化しているところが本当に多いので、お店だけをうまくセパレートできないっていう現状もあります。」

―家と店が一体化しているというのは、確かに難しそうですね。
原田さん「だからうちのブルワリーは、建物的には一体化していますが、醸造所と居住スペースは壁を作り区分けをしっかりしました。それは、たとえ息子が継いでくれなくても、誰かビールをつくりたいという人が現れたとき、その人に引き継げるようにと思ったからです」
ISLAND BREWERY の未来

ー将来的なビジョンについて、どのようにお考えですか?
原田さん「正直まだ迷っているところですね。僕は地域に貢献しながら自分のしたい仕事をしたいって思うと、やっぱり今の規模感でビールをつくるのがたのしいんですよね。いろんな副原料を使いながら実験的にビールをつくるのが好きなんです。ただ、これ以上、規模を大きくしてしまうと、その楽しさが薄れてしまうかもしれない。それに、スタッフが増えることで、人を抱える負担や、社長としての役割ももっと出てきますし、ビールもどんどん売らなきゃいけない。そうなったときに果たして僕は、仕事をたのしめるんだろうかとは思うんです。だから規模を大きくするというより、横展開はどうかと思っています」
ー横展開とは?
原田さん「たとえば今後は、ビールだけでなく、町の活性化につながるような事業展開ですね。ホテルや飲食店を作ったり、グループという言い方になるのかはわからないんですが、ちがった形で売り上げをつくるのもひとつの手じゃないかなと思ったりしています。まだまだ決まっていない構想段階ですが、ビールを主軸とした町の活性化を進めていきたいと思っています」

ー確かに、大きくするといろいろなことを考えてしまうジレンマなど出てきますよね。横展開おもしろそうです。
原田さん「今では設備の話でいうと、製造量を上げるというより、品質向上のための設備投資に力を入れています。将来的にはより良いビールを提供しながら、事業の拡大も視野に入れています。それは、長い目で見たとき、品質の良いビールをつくればお客さんやファンは着いてきてくれると思っているからで。ただ、売り上げが上がったときじゃあ増産するのかといった話になると思いますが、それはまだ未確定ですね」
ー赤裸々にお話いただいてありがとうございました。どんな形であれ、今後のISLAND BREWERYの動向がたのしみです!
酒造だった当時。タップルームの場所は販売スペースで、学校から帰ると角打ちスペースで酔っ払ったおじさんがお酒を楽しんでいるのが日常の光景だったそう。
そんな場所に新たに島を盛り上げようと立ち上がったISLAND BREWERYは、島の人の新たな職場になり、居場所になって、島外の人たちが来る理由にもなっています。

最後に、一番の理想として、ISLAND BREWERYのビールをどこで飲んでほしいか聞いてみました。
原田さん「最終形としては、家で飲むビールの選択肢になっていたらと思いますね。今、日本で言うと、食卓でビールを飲むとき、クラフトビールっていう選択肢ってあんまりないと思うんですよ。ただ、アメリカに焼酎を販売しに行っていたとき、スーパーに立ち寄ったら10mくらいの冷蔵庫びっしりのクラフトビールが並べられていて衝撃を受けたんですよね。まだまだ日本って、食事のときにはラガータイプのビール一択のところがあるので、食事に合わせてビールを選ぶような時がくればいいなと思っているんです」

ーてっきり、島に来てビールを飲んでほしいとおっしゃるのかと思っていました。
原田さん「もちろんそれが壱岐の観光にもちゃんと寄与できるようにその想いもあります。ただ、その手前としては、壱岐島に来ていただいたり、長崎のいろんな飲食店でうちのビールが飲めるようになればいいなと思っています。ただ、最終的なISLAND BREWERYのビジョンは、食卓でクラフトビールを楽しんでもらう、その食卓で、ISLAND BREWERYの食に合わせたビールを選んで楽しんでいただけたらいいなと思っていますね。長期な視点でいくと、ISLAND BREWERYの“魚に合うビール”がその一端を担えたらうれしいですね」

原田さんのことばの一つひとつからは、終始壱岐島のこと、壱岐島に来てくれるお客さんのことなど、壱岐島で働く人や壱岐島を取り巻く課題、未来のことなど、多くのことを考えて行動に移されているのがひしひしと伝わってきました。
その結果生み出されるビールは、その想いを投影しているかのように透き通った美しい一杯となって、多くの方の喉を潤しています。
そんな「ISLAND BREWERY」のビールを壱岐島中に連れ回して楽しんでみる第3回のコラムもお届け!ぜひ島に来て、IBのビールを堪能してみて!
ISLAND BREWERY が気になったら…

「ISLAND BREWERY」のビールは、公式オンラインショップで購入することができます。
また、壱岐島・勝本町にあるタップルームでは、「ISLAND BREWERY」のビールを6タップで提供中! 365日年中無休で営業しています。壱岐島に訪れた際には、ぜひ立ち寄って、「ISLAND BREWERY」の世界観をたっぷりと味わってみてくださいね。
公式オンラインショップ
タップルーム公式HP
\ 合わせて読みたい /




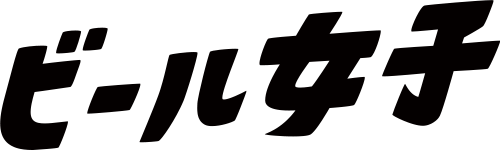
 お酒は二十歳になってから。
お酒は二十歳になってから。