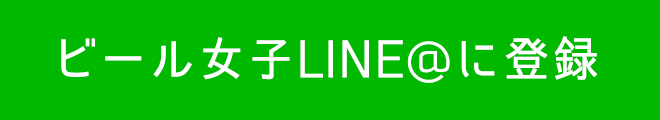この世に数え切れないほどの映画があるように、ビールだって個性あふれる味わいがたくさんあります。ほろ酔い気分の金曜日の夜に、ビールと映画のお話に舌鼓を打ってみませんか? お酒片手に物を書くビール女子、植井皐月のエッセイです。

我々はなぜ、酒を飲むのだろう。前夜の忘れ形見の空き瓶の列を眺める朝、何枚もの札が忽然と姿を消した魔法の財布、鞄の奥底から出てきた謎の電話番号。数々の過ちを犯し、いくつもの罪を重ね、それでもなお、なぜ我々は酒を求めずにはいられないのか。
そんなの簡単だ。現実をよりイカしたものにするため。アルコールは最も手軽で最も味わい深いドーピング剤みたいなものだ。元気が出るし、愉快な気がする。スタート地点が満たされていようと乾いていようと、そんなのまるで関係が無い。大きめのひと口を喉の奥に落とし込んだ瞬間から、右肩上がりはほぼ間違いない。これは一般論というよりも、ごく個人的な経験として。

私の愛するビールには「アルコール中毒による幻覚症状」という名前がついている。何度呼び返しても、この名前を授けた創造主のセンスには脱帽せずにはいられない。光よ、と神は言った。そして「デリリウム」と、彼は言ったのだ。
度数9%、ポップな外観とは裏腹に、比較的ヘビーな部類のビールだ。金色の液体が私たちを誘惑し、半ダースほどこれが空く頃には気分軽快になっている。デリリウムを感じるには、まだ幾種類か口に含まなくてはならないものがあるだろうが、少なくとも助走をつけるに不足はしない。濃厚な味わいと独特の癖が、私たちを喜ばせてくれる。

マーティン・スコセッシ監督「ウルフ・オブ・ウォールストリート」という映画がある。私の知る限り最上の、イカれた映画だ。酒(そして適切とは言い難い用途で使用される錠剤)によって主人公は常にハイになっており、その躁状態で数え切れないほどの大金を稼ぎあげる。女を抱き、鼻から白いものを吸い、そして幾本ものボトルを空にして、欲望の限りを尽くしていく。そして圧倒的なデリリウムを感じながら生きるのだ。その身を滅ぼすまで。
現実が現実だけで存在することにどんな意味があるのだろうと、私は時々強く思う。現実が見せる幻影があり、現実を越える夢があり、現実に塗り重ねるデリリウムがある。日常というのは常に、それら「現実ではないもの」との混濁状態の中で成り立つものではなかったか。

さあ、栓を開けよう。グラスを満たそう。そして陽気に歌おう。記憶の海に飛び込み、理想の山を登ろう。見上げた星がいつも以上に強く瞬き、横で眠る誰かの声がより魅惑的に聞こえだすころ、デリリウムはすぐそこまで近づいている。
飲もう。夏が終わったことなんて私たちの理由にはならない。