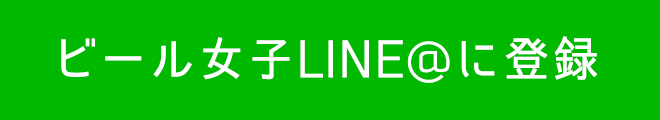この世に数え切れないほどの映画があるように、ビールだって個性あふれる味わいがたくさんあります。ほろ酔い気分の金曜日の夜に、ビールと映画のお話に舌鼓を打ってみませんか? お酒片手に物を書くビール女子、植井皐月のエッセイです。

雨の季節になった。じっとり纏わりつく空気や、窓の外から注ぎ込む物悲しい音。友人たちは笑うけれど、この四季からも外れたひと月ばかりの短い季節を、私は好む。雨の香りが好きだからだろうか。寂しさと甘やかさが混ざったような気持ちで、陽光の届かない真昼を過ごすのがたまらない。長くはない季節だと、分かっているからかもしれない。
6月の結婚のことをジューン・ブライドと呼ぶのだということを初めて知ったとき、私はまだ恋のひとつも知らないくらいに幼かった。その頃はこの雨の季節にそう思い入れも無く、素朴な心で率直に思ったのは、どうしてこうも雨の多い季節の結婚が特別視されるのだろうということである。幼い私にとって季節は日本のそれだけで、花嫁には青空だけが似合うものと思い込んでいた。
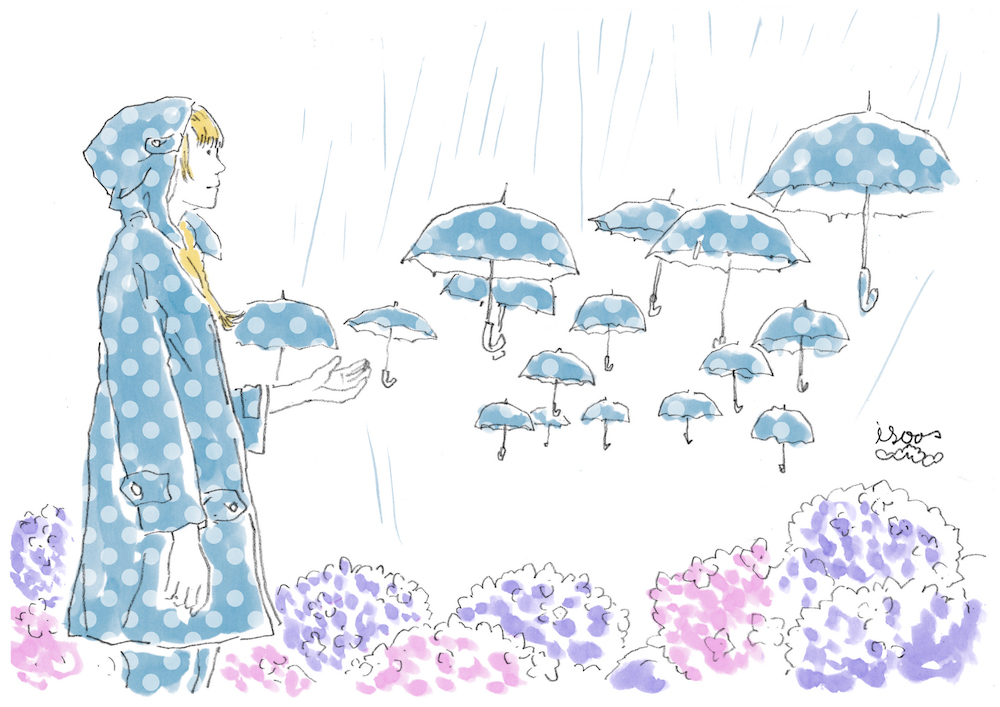
ビリーとレイラという、ひと組のカップルがいる。ヴィンセント・ギャロ監督「バッファロー’66」という映画に出てくる、どうしようもないふたりだ。大人になった今彼らを想うとき、彼ら以上に6月の結婚にふさわしいカップルはいないと確信している。
ビリーの性格を端的に表すのであれば、ナイーヴな癇癪持ちだ。傷つきやすく、自分に甘く、寂しがり屋で、しかしあと一歩自分への肯定感が足りない。だからその全てを、偽りや周囲の人間で埋めようとする、実に厄介なタイプの男だ。
レイラの性格は、そんなビリーにたった一夜で「愛している」と告げてしまうタイプとでも言えば、それが一番分かりやすいだろう。しかも二人の関係はビリーがレイラを誘拐したことで始まる。
全体的に薄暗いトーンの映像、湿っぽく情緒不安定な二人の様子、そこに重なる印象的な音楽や何度も視点が切り替わる映像の調子。そういったすべてのものが、私にこの雨の季節を思い起こさせる。

この映画を見ているとき、甘ったるいものや高度数のビールはまるで飲む気がしない。おそらく画面から伝わる湿度と濃度が高すぎるのだ。冷蔵庫を開け、幾種類もの用意があるビールの中からつい手に取ってしまうのは、苦みがあるものや飲み口の軽いもの。あるいは「ギネス」がキンキンに冷えていれば、何の不足もない。
グラスにざくざくと氷を放り込み、そこに「ギネス」を注ぐ。あのクリーミーな泡が少し多すぎるくらいに立ち上り、それらが落ち着いて氷が少し溶けたくらいが、この映画に添える「ギネス」としての一番の飲み頃だ。独特の苦みと氷が交わる絶妙な清涼感が、どうにか映画を中和してくれる。

弱くて、ずるくて、理不尽で。寂しくて、甘えたくて、愛したくて。そんな二人が体の関係を持つことさえなく、服を着たままぎこちなくモーテルのベッドで寄り添うシーンは、この映画で一番の絵だ。
彼ら以上に、6月の結婚に相応しい者たちを私は知らない。出来ることなら、寄り添う彼らの姿が永遠に続けばいいと思う。この雨の季節が、決して長くは続かぬものであろうとも。この地上に降り注ぐ間だけ、雨は永遠に思える。