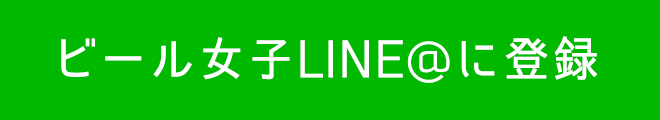この世に数え切れないほどの映画があるように、ビールだって個性あふれる味わいがたくさんあります。ほろ酔い気分の金曜日の夜に、ビールと映画のお話に舌鼓を打ってみませんか? お酒片手に物を書くビール女子、植井皐月のエッセイです。

眠りと現実の狭間では、時に妙なことが起こる。その現実が酔いの効果で波打ってでもいればなおさらだ。
以前、ビールをたくさん飲みたいがためだけに、ひとりベルギーまで足を運んだことがある。朝からひたすら高アルコールの本場ベルギービール飲み続けていた私は、昼すぎ頃には身の危険さえ感じる立派な「酔っ払い」に進化し、昼寝をするためにホテルへ戻った。ホテルに帰るまでの道中でさらに何本かのビールを調達することは忘れなかったけれど、いざホテルに着くとビールを冷やすことなどすっかり失念し、私は眠りに沈んだ。

どれくらい時間が経っただろう。ふと目を覚ました時、部屋はいくつかのランプが付いたままになっていた。ベッドの横には小型のテーブルがあり、そこにはビールが雑に並べられていた。すると、その中の1本と、私はふいに目が合った。そのビールのラベルでは色気の香り立つお姉さんが背中を露に横たわっていて、こちらを魅惑的に見つめていた。私に気がつくと、彼女は私に向かって微笑みを浮かべて見せた。
彼女の名前は「リンデマンス ペシェリーゼ」。まるでキャンディーのような強いピーチの香りと、ランビック特有の強い酸味がカラフルに融合する、実にポップな1本だ。ビールであるのにコルクで栓がされているのもまた可愛らしい。彼女を飲むのは楽しかった。私達はいくつかの会話をし、彼女は終始リラックスした様子で寝そべっていた。

それからしばらくして、日本に帰った私はある映画を観た。その時には彼女との思い出はすっかり記憶の奥に仕舞い込まれていて、思い出すこともほとんどなかった。しかし何の気なしに選んだその映画は、私の記憶から実に的確に彼女を連れだしてきた。
映画の名前はジャン=ピエール・ジュネ監督「アメリ」。ビビットなパッケージとレトロポップな映像美で一世を風靡した作品だ。パリ・モンマルトルで生きるアメリという若い女性が主人公で、彼女は現実と空想の入り混ざった、あるいは幾分か空想に重心を置いた日常を生きている。

映画の中で、写真の中の人間は動き、置物は語る。それはまるで、私が出会った彼女のように。
その後、私は日本の酒屋で再び「リンデマンス ペシェリーゼ」を見つけた。それはお行儀よく冷蔵ケースに陳列していたけれど、もう彼女と私の目が合うことはなかった。そこに陳列していたのは、同じビールであって彼女ではないのだ。
できることなら、また彼女に会いたいなと思う。そして一緒に「アメリ」を観たいと思う。彼女と会話をしながら観る「アメリ」は、大層愉快なことだろう。