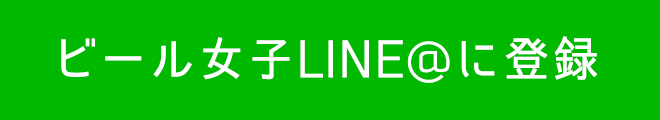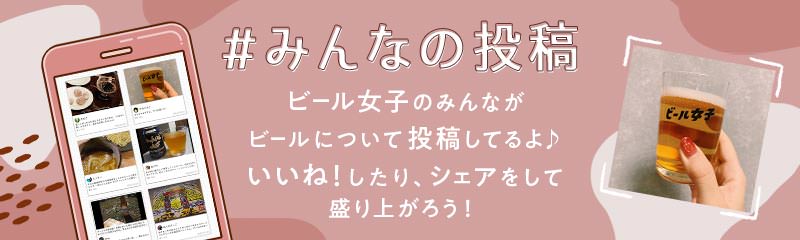この世に数え切れないほどの映画があるように、ビールだって個性あふれる味わいがたくさんあります。ほろ酔い気分の金曜日の夜に、ビールと映画のお話に舌鼓を打ってみませんか? お酒片手に物を書くビール女子、植井皐月のエッセイです。

青い薔薇は、不可能という意味の花言葉を持つ。存在しない、作ることが出来ない、きっとそんなところから、この花言葉は付けられたのだろうと思う。あるいは青というのは、そういう存在しないもの、しかしそれでもなお求めずにはいられないものに対する代名詞のような色なのかもしれない。
その青を名前に冠したビールがある。それは「ブルー・ムーン」、オレンジピールが際立つ非常に甘やかなビールだ。もちろん、グラスにはライムではなくオレンジを添える。

青い月というのはどういう月なのだろうと、「ブルー・ムーン」を飲みながらわたしは時折考える。幻想的なもの、手に入らないもの、彼方にあるもの、だけど欲しいもの。月というものが本来持つイメージも相まって、そんなことが頭に浮かぶ。ひとつだけ確かに言えることは、青い月は間違いなく良いものであるはずなのだ。例えば遠い幼い日に、星や月に手を伸ばした記憶のように。「ブルー・ムーン」を一口でも飲んだことがあれば、青い月にシニカルなイメージを抱けるわけがない。
彼女の見た月は青かったのではないかと、思う人がいる。それはホリー・ゴライトリー。「ティファニーで朝食を」に登場する、きらびやかな彼女だ。月なんて見えるはずのない太陽の下で、彼女は空を見上げてムーンリバーを歌っていた。

家出としか言いようのないやり方で夫との関係を強引に解消し、世話になった芸能事務所からは大一番の前日にひらりと逃げ出す。生まれながらに与えられた名を捨て、定職を持たず、男たちが与えてくれるチップでその日暮らしを送る。彼女が持っているものは華やかな衣装と装飾品、自分を着飾るためのメイク道具くらいのもので、家具のひとつもありはしない。一見すると、彼女は実に自由だ。どこへでも行けるし、何物にも縛られない。
「君を愛している」と言うかつての夫に、彼女は言った。「それがあなたの弱いところよ」と。彼女にとって愛することは縛ることであり、愛さずにいられないことは愚かなことなのだ。どうしてか、それはいつか失われてしまうからだ。正確にいうのであれば、失われてしまうかもしれないものであるからだ。何かを愛することというのは、おそらく勇気であるのだろうとわたしは思う。何かを失うかもしれない勇気であり、傷を引き受ける勇気だ。彼女には、その勇気がなかった。本当は、装飾品でない愛が欲しくて仕方が無いというのに。

この映画の中で、最終的に彼女はひとりの男性との間に愛を見出す。それでも、もし私が彼女に出会うことがあったなら、ムーンリバーを歌う彼女の隣で、一緒に「ブルー・ムーン」を飲みたいと思う。この世の誰しもが彼女のように愛を手に入れるとは限らないけれど、それを求めてしまう気持ちだけは、誰しもの心の奥底に存在するのではないだろうか。青い月は、今日もひっそりと陽光の中に隠れている。

 お酒は二十歳になってから。
お酒は二十歳になってから。